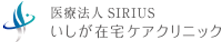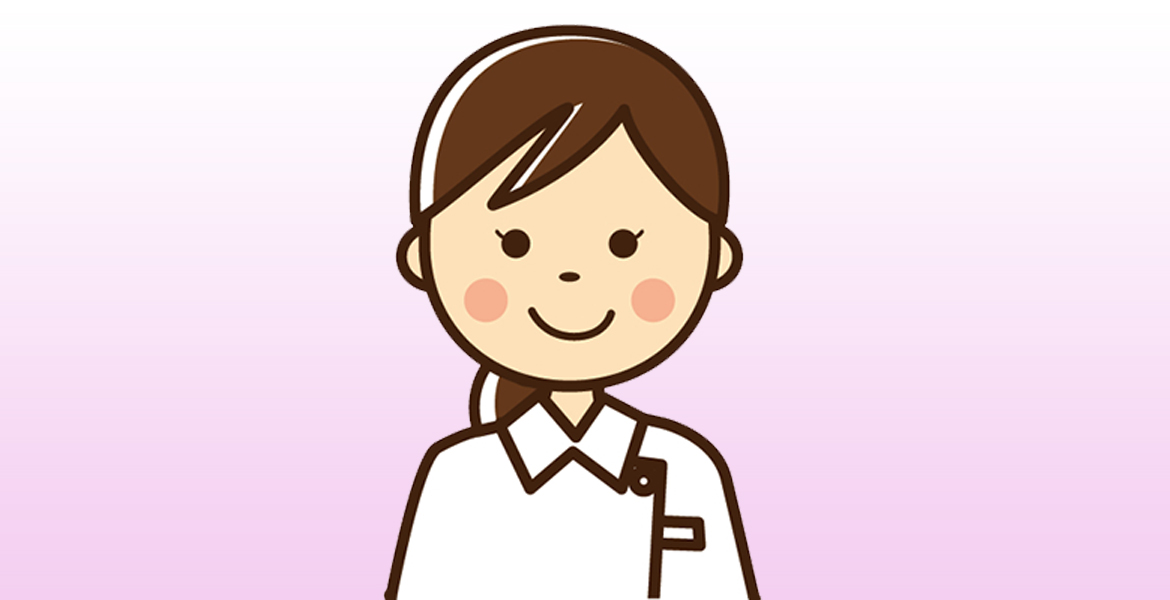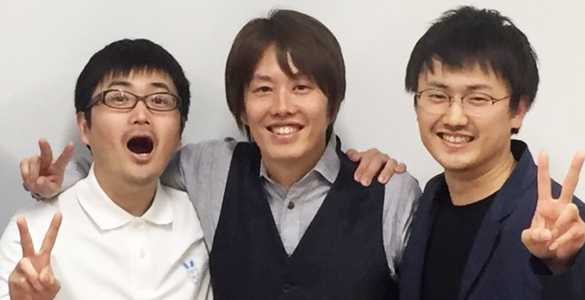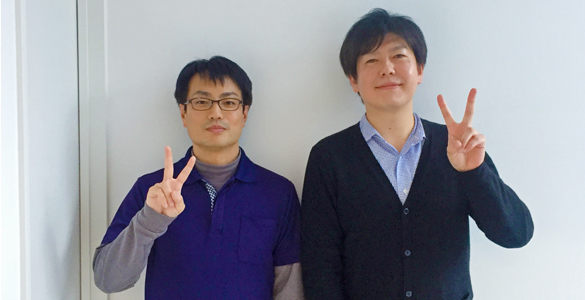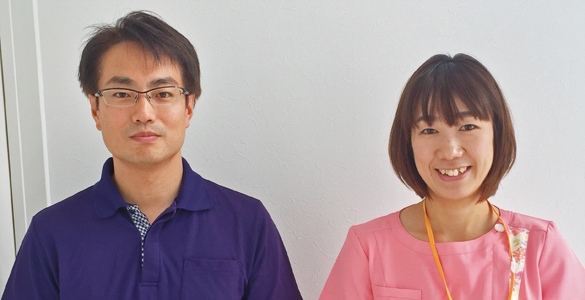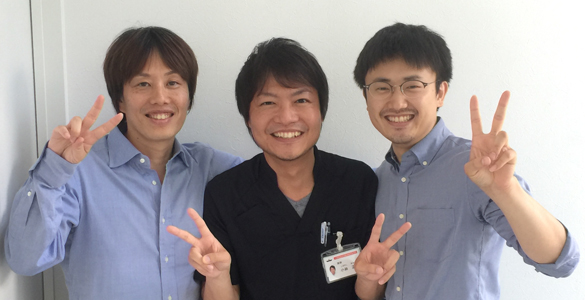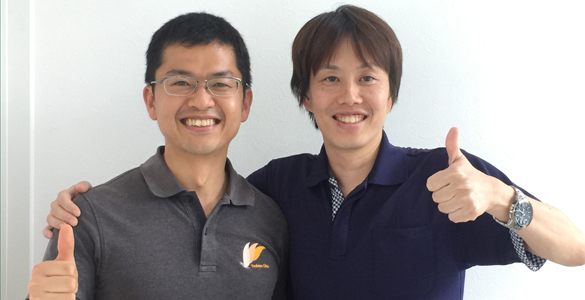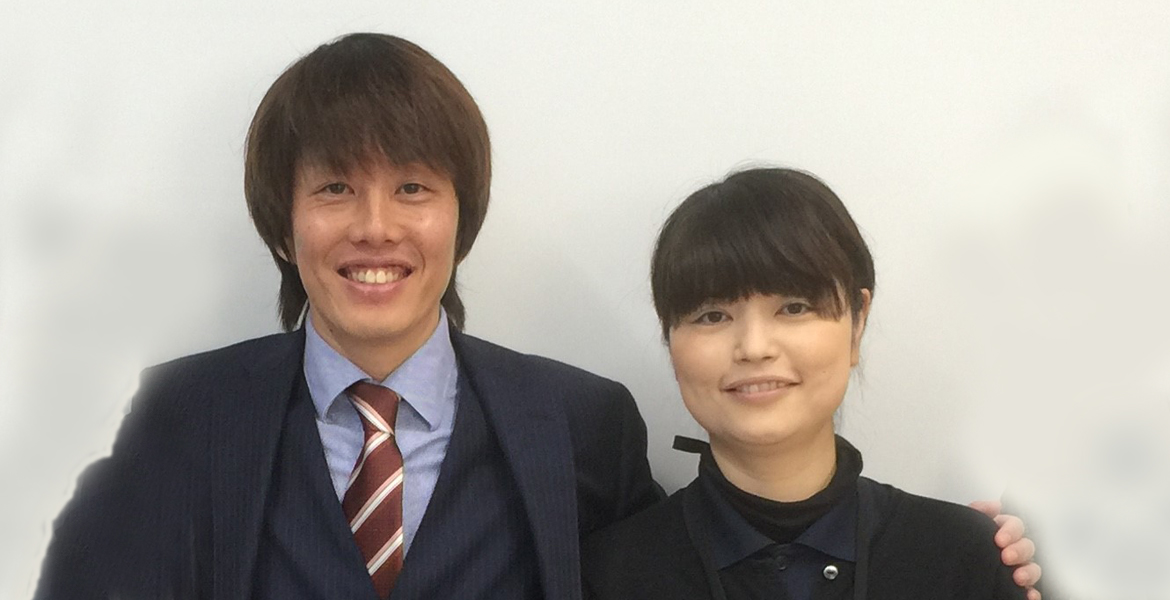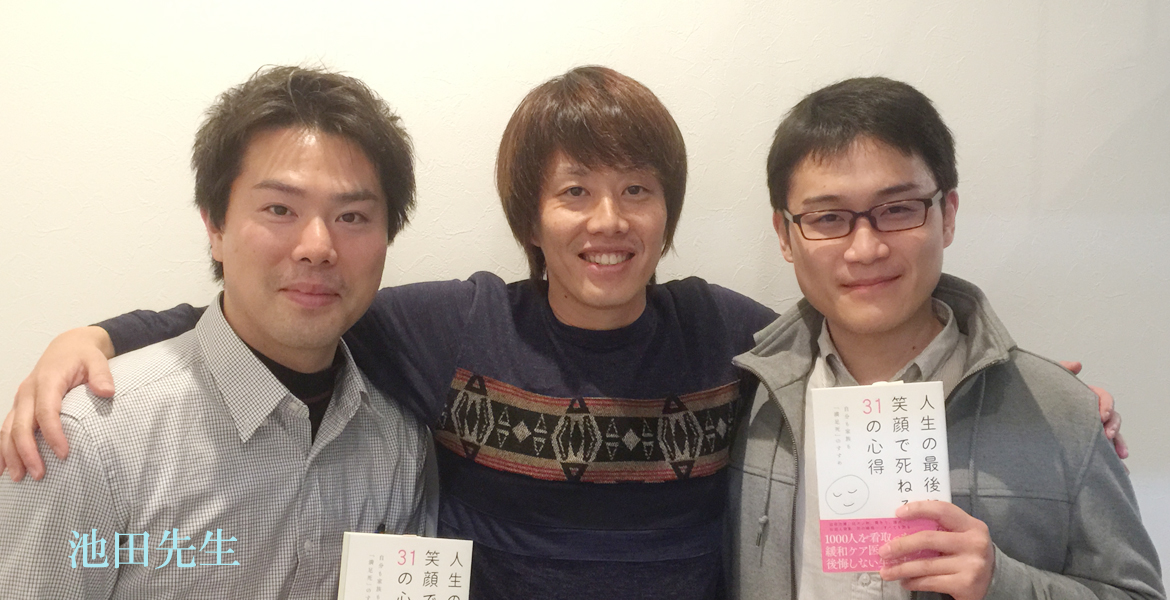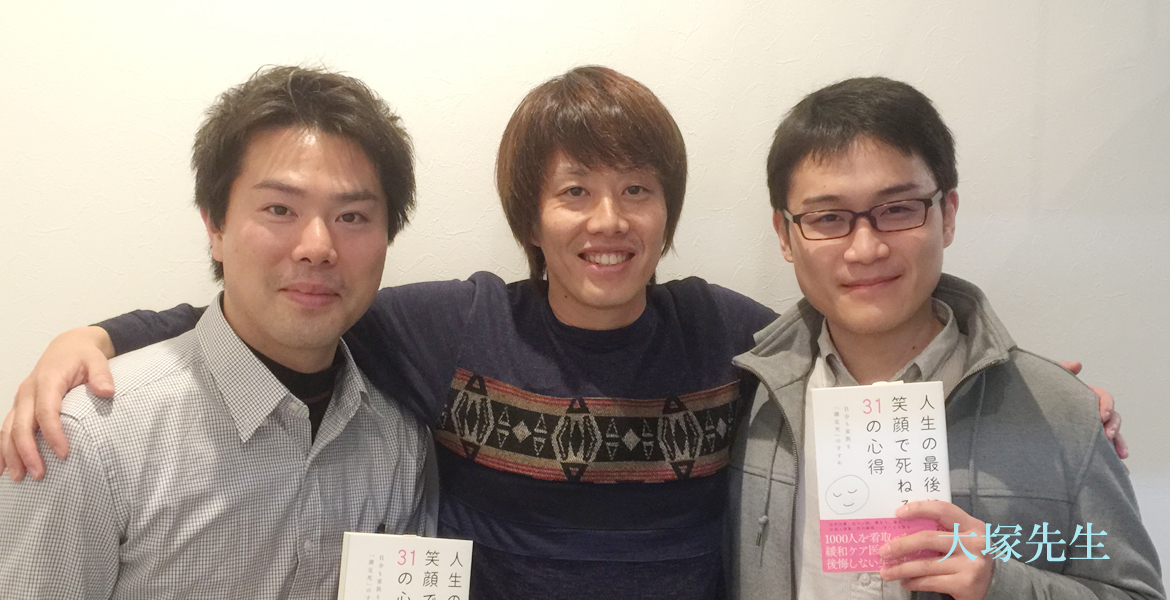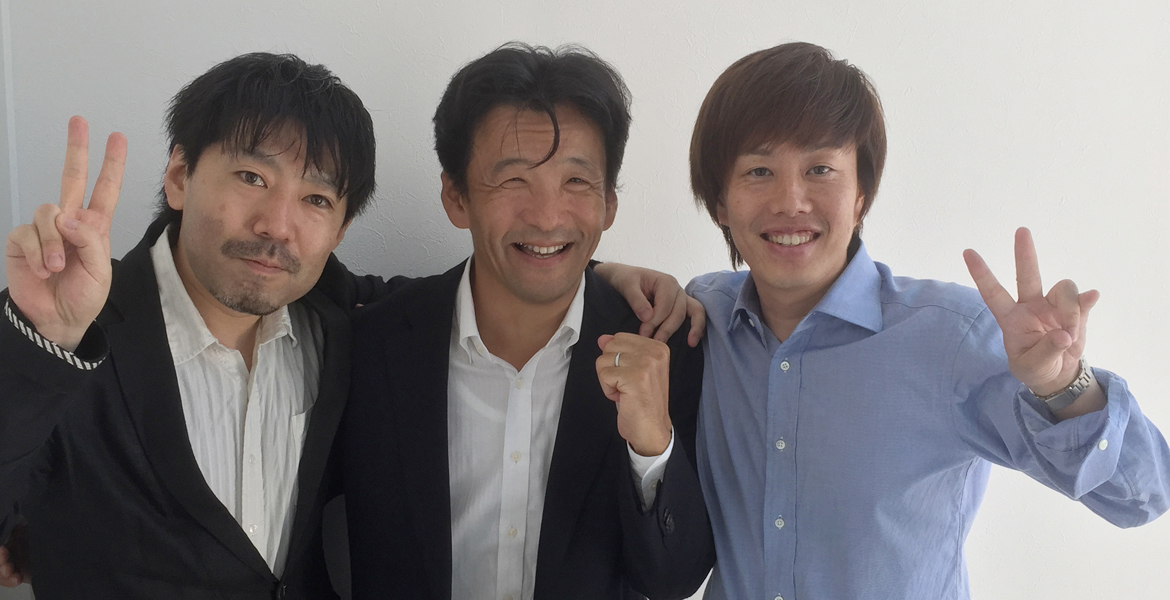高速道路を降り森の田舎道を抜けていくと瀟洒な建物が目に入ってくる。「うぉーすごい」思わず感服する。大きな横長の窓は自由で開放的でナチュラルな内部空間を映し出し、まるで近代建築家ル・コルビュジエが手掛けたようだ。
感動しつつ、クリニック内部に案内いただくと、在宅訪問のスタッフが機能的に動ける動線や効率的な物品管理のありさまがすぐ目に飛び込んでくる。2階はまさしくピロティ―!壁のない開放的な広い空間はまさにファサード!柱さえ熱帯魚が泳ぐニッチとなって視界を遮ることはない。階段は大学の講義室を模し、木の滑り台やカプセル空間、ハンモックのある休憩室などが遊び心を促し、さらに医療機関の緊張感をほどいてくれる。緊張して外来に来られる初診の患者さんも先ずは場に癒され、そして石賀先生の前向きで優しい声かけに安心されたようだ。
訪問診療に出向けば、先生や看護師、スタッフが代わるがわるに患者さんに笑顔で声をかけながら効率的に診療処置を進めていかれた。痛みや苦痛も軽減されて自宅で安心して過ごされているようだ。患者本人はもとより家族も心から頼りにされていることが伝わってきて、患家の出先でも安心感や癒しを届けているのだとわかる。良質な在宅医療はリーダーはじめスタッフの人間性が反映されるものだ。
データも素晴らしく、北勢地域の幅広い地域を網羅し、年間450人を超える日本トップクラスの看取り数を出し看取り率9割、そのほとんどが癌や病態の重い方だそうで、質だけでなく量的にも日本の在宅医療の先端を走っている。医療情報をこまめにニュース新聞としてまとめ、栄養や免疫力の向上、生活支援の知恵、最期の心構えなどをわかりやすく提供されていた。なるほど地域に根ざした活動を丁寧にされていることも信頼されている理由なんだ。
ほどなくクリニックに戻り、管理栄養士が作られる昼食をレストランのようなキッチンでいただき、ほっこりした。
1週間のお看取りをスタッフ全員で振り返るデスカンファレンスにも参加した。いろいろな機会を設け、スタッフが集う場や時間を演出して大所帯の求心力を高めるなど、マネジメントも抜かりがない。全国から見学や研修、取材が絶えないのは、ここ「いしが在宅ケアクリニック」の魅力がいっぱい輝いて、学びとなっているからなのだろう。
今日研修をさせていただく機会をいただき、とても真似はできないものの、それぞれの地域に応じて、そこに暮らす人々を魅了する在宅医療の創造がポストコロナの社会には必要になってくるのだろう。このような機会をいただいたことに石賀先生はじめスタッフの皆様に感謝します。
- Tel (059) 336-2404
- Fax (059) 336-2405
- Access
0
0
0
0
これまでの見学者
これまでお越しいただいた方の分類(2024.6.12現在)
見学・研修者の声
当院の見学・研修の感想
当院の見学を希望される方々が、各方面からお越しになります。様々な職種の方と当院の活動を一緒に見学して頂き、 私たちもモチベーションアップに繋がっております。ご縁がございましてご見学・研修いただいた方の声を掲載させて頂きます。
見学を受けての感想
- By: 寺澤亜希 様
- 3.Jul.2019
- 管理者・看護師 訪問看護キープオン 守山
先日はお忙しい中、見学同行を受けて頂きありがとうございました。
今回、知人を通して先生の人柄に感銘を受け、著書を読ませていただきました。
同じ在宅医療従事者として、家だからできること、家だから叶えられることに共感を覚え、見学の希望をお願い致しました。
石賀先生に同行させていただきました。その訪問は全てにおいてゆとりと利用者家族に与える安心感、時間の共有にありました。
先生と一緒に将棋が出来た利用者の満面の笑みは、薬以上の治療を施しているように見受けられるほどでした。
朝の申し送りから、訪問のお知らせの電話対応まで医師が対応され、常に待つ身である利用者への配慮がなされていました。
また、訪看やケアマネとの連携も密で、レスポンスの速さと貴院スタッフの情報共有のあり方を傍らで見せて頂き学び多い見学となりました。
地域で支え合うことができる在宅医療の理想形を実践されており、本当に目から鱗の一日になりました。
お忙しい中ご対応いただきありがとうございました。学びを次に繋げていくことができる様、精進したいと思います。
本当にありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。
皆様へ
- By: 石黒謙一郎 院長、小此木真由美 様、松田葵 様、堀籠未央 様
- 11.Apr.2019
- Doctor いしぐろ在宅診療所 医療事務、看護師、言語聴覚士
院長 石黒謙一郎 先生より
この度は、年度初めのお忙しいところ、我々の見学を受けて頂き誠にありがとうございました。私が在宅医療に興味を持ち勉強していく中で出会ったのが、石賀先生の著書でした。そこで以前貴院へ見学させて頂き、「僕がやりたいのはこれだ!」と衝撃を受けたことを鮮明に覚えています。そしてこの度、在宅診療所を開業することとなり、原点回帰ということで貴院を見学させて頂きました。開業スタッフには在宅医療の経験がない者もおりますが、貴院での見学で、私の目指していきたい在宅医療を体験できたのではないかと思っております。懇親会でも、スタッフの方々にいろいろな話が聞け、とても勉強になったようです。また、お食事もごちそうになり、誠にありがとうございました。
これから、貴院を目標に地元豊田市で在宅医療を行っていきたいと思います。
今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。
医療事務 小此木真由美 様より
今回は訪問診療に同行させて頂き誠にありがとうございました。診療の同行は今までも経験はありましたが、今回の伊藤副院長先生の患者さんに対する接し方がすばらしく、とても感銘をうけました。患者様、ご家族様からのお話をゆっくりと時間をかけて聞いておられ、病状説明に関してもゆっくりとわかりやすく説明されている姿を拝見し、とても感激いたしました。また、退院前カンファレンスにも参加させて頂き、契約の様子を見させて頂いたこともとても勉強になりました。また、事務としては、年4回のクリニック誌の作成はとてもよい取り組みだと感じました。実際に各病院、事業所へ手渡しで持っていかれているということを聞き、そのような地道な取り組みがクリニックを支えているのだなと感じました。クリニック誌は、ぜひ当院でも作成していきたいと思います。この度は見学を受け入れていただきありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。
看護師 松田葵 様より
在宅医療をしたことの無い私にとって今回、いしが在宅ケアクリニックで見学させていただく目的として同行看護師としての役割を中心に見学させていただきました。
見学させていただいた訪問診療では同行が看護師ではなかったですが相談外来後の家族への説明の仕方・関わり方、一日の流れについて教えていただくことで同行看護師のあり方について少しでも理解できたように思います。
今まで急性期病院でしか働いたことの無い私にとって看護師の仕事は看護師で、医師の仕事は医師で、事務の仕事は事務でという考え方でしたが在宅医療で多職種と関わっていくには看護師の業務だけではなく他の職種のことについても理解していなければ患者様にとって良い在宅医療が提供できないということを学ばせていただきましたので良い医療が提供できるように学び続けていただきたいと思います。
言語聴覚士 堀籠未央 様より
在宅医療に携わる言語聴覚士がまだまだ少ない中で、摂食嚥下のニーズや地域のリハビリとの連携を中心に見学させていただきました。嚥下機能障害が疑われる患者には歯科、口腔外科との連携がスムーズにおこなわれており、構音訓練や嚥下訓練は歯科衛生士が担っていました。医療の介入に消極的な家族に、患者が食べることによる誤嚥のリスク、食べないことによる口腔機能の低下のリスクをどのように説明し、理解してもらい、意思決定をおこなったのか、説明する人によって選択の幅が広がったり狭まったりしないようにしたいと思います。最期まで、食べたいものが食べられるようにお手伝いしていきたいと思います。
皆様へ
- By: 開田脩平 先生
- 25.Mar.2019
- Doctor みらい在宅クリニック港南
先日はお忙しい中、見学を引き受けていただき、ありがとうございました。
朝のカンファレンスでの申し送りでは先生方が夜間や休日を問わず、必要となれば往診に行き、診察をしたうえで治療を行っているということを知ることが出来、大変勉強になりました。医師がしっかりと診察に行くことが自宅での看取りにつながるのだなと再認識しました。
昼過ぎまで門間先生の訪問診療に同行させていただきました。状態の悪い患者であったり、訪問診療を開始したばかりで不安の多い患者に対して医療だけではなく、日常生活の話も交え、親身に、そして時間をかけて診療するスタイルは自分も見習うべき点が多く、今後の自分に診察にも生かしていこうと思いました。その他訪問診療の在り方であったり、ICTの活用法など様々なことを移動中の車内で話が出来たことはとても有意義でした。
午後の診療では石賀先生の訪問診療に同席させていただきました。状態が悪化した患者の家族への面談内容はとても分かりやすいだけではなく、家族みんなを集めて話を聞いてもらうというのは今までに経験したことがなかったためとても参考になりました。私もこの1か月間で数名の患者の自宅での看取りに関わりましたが、石賀先生のおっしゃっていたように、面談や診察する際は孫たちなど小さい子供も同席するようにしてもらい、最期息を引き取る場面でも小さい子供たちにも説明をしてあげるようにしました。小さい子供たちにとってこの経験は貴重なものになると思いますので、私も今後はこの診察方法を取り入れていきたいと思います。
事務所に戻ってからは石賀先生がどのような思いで、どういった内容の講演をされているのか丁寧に教えていただき、とても参考になりました。医師会だけではなく、小学生や様々な職種の方たちに感動してもらうような資料を作られており、今後自分もそのような資料を作れるように努力していきたいと思います。
最後には常勤の先生方といろいろと意見交換をすることが出来ました。参考になる部分もあれば、自分たちでは当たり前に行っていたことが珍しいことであったり、様々なことに気づかされ、とても貴重な時間を過ごすことが出来ました。
忘れ物をしたため、事務長には2度も駅まで送迎していただき、ありがとうございました。
今回の見学を通して西日本一のクリニックである所以を知ることが出来、とても有意義な見学になりました。4月より私自身もみらい在宅クリニックで勤務し、いしが在宅ケアクリニックに負けないよう日々の診療を行っていきたいと思います。クリニックが新しく移転した際にはまた見学に伺わさせていただきます。またもしなにかの用で横浜に立ち寄った際はお声掛けしていただければみらい在宅クリニックと横浜の街をご案内いたします。
この度は本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
いしが在宅ケアクリニックのスタッフの皆様
- By: 滝口萌絵 様
- 8.Mar.2019
- 愛知淑徳大学 心理医療科学研究科心理医療科学専攻臨床心理学コース
先日は、貴重な体験をさせて頂き、ありがとうございました。
朝の情報共有のミーティングと外来の見学や、訪問診療に同行させていただき、実際に先生方、患者様とお会いして、お話しすることが出来ました。
朝のミーティングの中で真剣な表情だった先生方が、患者様に出会うときは穏やかで明るくお話しされている姿を見て、在宅ケア・緩和ケアに対して私が持っていた苦しくて重たいイメージが、大きく変わったように感じます。自宅で看取ること、看取られることの意味を学ぶことが出来ました。何より、死を距離のある実感のないものにせず、遠ざけずに理解していく姿勢を、勉強させていただきました。
以前見たある映画の1シーンに、「死を遠ざけることではなく、生を高めることが医者の務めだ」という言葉がありました。様々な性格、生き方、選択がある中で、数少ない人間の共通点の一つに、死があると思います。ですから、死は多くの苦痛や悲嘆を生むものでもありますが、忌むべきものかと言われればそうであるとも断言できず、ただそこにあるもののようにも感じます。その訪れを受け入れるには、喪失を惜しみ、別れを悲しみ、さよならの作業をすることが大切です。これは、おそらく死を迎える人自身にも当てはまりますし、その周りの人々にも当てはまることなのではと思います。
在宅での緩和ケアは、死の近くにいる方の「生を高める」作業であり、その周りの人にとってのさよならの作業の一つのように感じます。もちろん、その作業の形は人によってそれぞれ異なってくると思いますが、在宅ケアは生きることと死ぬことを間近に感じるとても大切なものだと、この度の見学を経て、学ぶことが出来ました。これからもっと広く、多くの方に、選択肢の一つに在宅ケアがあるということが広まっていけば、と思います。
また、石賀先生がお話ししてくださった中に、「地域連携」を大切にされているというお話がありましたが、地域で患者様を支えていくためには、多くの専門職や、地域住民の方の協力が不可欠だと思います。専門職だとつい自分の専門に閉じこもって閉ざされた狭い世界を選択しがちですが、自分の活動を発信し、信頼関係を作っていくことも、その地域で生活する患者様、クライエント様を助けていく力になると学びました。
今回の経験から学んだことを活かして、これからも勉強して参りたいと思います。
最後になりましたが、この度はお忙しい中、見学から診療の同行まで、またとない貴重な機会を頂き、本当にありがとうございました。
いしが在宅ケアクリニックの皆さま
- By: 石本真澄 様
- 8.Mar.2019
- 愛知淑徳大学 心理医療科学研究科心理医療科学専攻臨床心理学コース
先日は、お忙しい中、見学させていただきありがとうございました。
訪問診療やミーティングまでしっかり見せていただき、医者でも看護師でもない私たちがここまで見せていただけるのかと率直に驚きました。石賀先生が「地域を育てることが大切」とおっしゃられていたように、在宅の存在を様々な人に広めることまで視野に入れていらっしゃるからこそ成せることなのかなと感じました。専門職を目指しているため、自身の分野を正確に伝え広めていく活動は見習うべきところが多くありました。
そういった視野の広さからでしょうか?クリニック内では、医師・看護師・事務といった役割だけでなく個性が大切にされた関わりがあるように見えました。個が大切にされるからこその様々な視点の共有・協力が繰り広げられることは素敵ですね。
また、訪問診療では、ターミナルケアへの「暗い」、「悲しい」といったイメージが変わり、それぞれの家族の「当たり前の暮らし」がそこありました。「悲しいこと」などと評価されるものではなく、それぞれが最後まで自分らしく悔いなく生き抜き、家族もその「死にざま」をしっかりと見届ける、そのためのお手伝いをしているといった印象を受けました。在宅だけが可能にすることとは言いませんが、「在宅という選択肢もある」ことは大きな違いだと感じました。
1日の見学でしたが、会ったことのないような人々との出会いを経験させていただきました。自分の知らない人と出会うことで様々な考えが深まるもので、心動かされる瞬間が沢山ありました。まだ、形にならない感情もありますが、今後知識を増やして形になればと思っております。ありがとうございました。
皆様へ
- By: 小原章央 先生
- 20.Feb.2019
- Doctor 医療法人 社団 都会 渡辺西賀茂診療所
昨日は大変お忙しい中、貴院の見学並びに訪問診療同行、また、多くのことを学ばせて頂きありがとうございました。
貴院に集う先生方が皆、在宅医療、特に緩和ケアを含め在宅で最期まで過ごしていただくことに、強い熱意とこだわりを持っておられること、そしてそれを同じ気持ちでスタッフの皆さんが支えていることを肌で感じました。
石賀先生の訪問診療の際の、患者さんとの距離の近さ、帰るときには必ず握手や体に触れて帰る姿、門間先生の初回往診での、本人やご家族の思いを聞きながらの話しの進め方、そしてそれを「普通のことをやっているだけ」とさらりとおっしゃられたこと、中村さんの組織の中での立ちふるまいとお話の中から伺えるマネジメントで気を遣っていること、全てが刺激になりました。
患者数や看取り数ではとても貴院に及びませんが、患者さんやその家族の紡いできたものがたりを大切にしながら在宅で最期まで過ごしていただくことへのこだわりは、うちも負けませんよ(^^)。
お忙しい中、本当にありがとうございました。
今後ともご指導賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
在宅医療の素晴らしさを実感しました。
- By: 山下祐美 様
- 25、26.Sep.2018
- 看護師 ねむの花 訪問ナースステーション
いしが在宅ケアクリニックの皆様、先日はお忙しい中、訪問診療に同行させて頂き有難うございました。
いしが在宅ケアクリニック様に伺わせて頂いた際は、とても緊張していましたが、皆様が心よく迎えて下さり、あたたかい雰囲気の中、とても優しい対応に安堵致しました。
患者様の情報共有、意見交換など、朝のミーティングを通して患者様が安心して自宅での療養が継続できるよう、多職種チームで患者様を支えておられることを痛感致しました。
また、同行訪問の際、先生方、看護師さんの患者様への丁寧な言葉かけ、患者様の思いにしっかり耳を傾けられている姿を見て、寄り添った関わりが、どれほど大切であるかということを、改めて学ばせて頂きました。
患者様の、とても嬉しそうに安心された表情がとても印象的でした。
今回、在宅医療の現場を見学させて頂き、患者様への先生や同行される看護師さんの丁寧な対応に感動するとともに、現場の大変さも実感致しました。
1日の流れを見学させていただき、多職種連携、情報の重要さ、心に寄り添う関わり等とても勉強になりました。
学ばせて頂いたことをステーションに持ち帰り、スタッフ間で共有したいと思います。
そして、今回の学びを生かして、患者様が安心して自宅で生活ができるような看護を提供できるよう努力していきたいと思います。
10月から、桑名市で、ねむの花訪問ナースステーションを開業致します。
ねむの花のキャッチフレーズである、【いつもあなたのそばに】を目指して、患者様一人ひとりの希望を叶え、寄り添う看護を目指していきます。
スタッフが2日間大変お世話になり、お忙しい中、本当に有難うございました。
今後とも宜しくお願い致します。
最高の見学でした!
- By: 小林正宣 院長
- 18.Jun.2018
- Doctor 葛西医院
病院見学第14弾として三重県四日市にある「いしが在宅ケアクリニック」を見学させていただきました。
在宅医療のひとつの形を示した「四日市モデル」となったこのクリニックは、約10年前に石賀丈士先生が四日市で開業されたことに始まります。
今では常勤10名の医師が月530名以上の患者さんの訪問診療を行い、毎月20名の患者さんをお看取りされていて、しかも患者さんの満足度が非常に高いという尋常じゃないクリニックです。今でもどんどん患者さんは増えています。
昨年、福永記念診療所の高井先生による関西在宅医療研究会で石賀先生の講演を聞いたときに、いつか見学に行ってその現場をみてみたい!と思ったことが今回の見学のきっかけです。
そのときの講演では石賀先生の素晴らしいプレゼンに魅了されながら、ひときわ惹かれたのは、その徹底した信念の強さでした。
患者さんが最良に満足できる在宅医療を提供することに妥協を許さないという気概を感じ、非常に感銘を受けたのを覚えています。
しかもスタッフが疲弊しない仕組み作りが出来ているということにも興味がわきました。
今年の在宅医学会で石賀先生に久しぶりにお声をかけさせて頂き、中村事務長のコーディネートのもと今回の見学が実現しました。
電車では朝のカンファレンスに間に合わないため、朝5時半に車で出発!
ほぼこちらが一方的に石賀先生のことを知っているだけという状況で、今までの見学の中で一番ドキドキしながら向かいましたが、最終的には心から訪問診療を楽しみつつ、刺激的な経験やアドバイスを頂くことができ、最高の見学でした!!
朝7時半にクリニックに到着して、挨拶も早々に朝のカンファレンスに参加。
その後は新規導入の患者さん家族との面談を見学させて頂き、看護師さんと事務さんによる、とても丁寧に時間をかけた説明にも同席させて頂きました。この丁寧な説明がとても大切であり、患者さんとの信頼関係の第一歩であることを感じました。
ほぼ丸1日を石賀先生の訪問診療に同行させて頂き、鎌田實先生や、中西重清先生との共通することを発見!!
それは、「患者さんを笑わせること」と「患者さんと握手すること」です。まるっきり一緒のことしてはるやん!!とちょっと興奮してました。
あ、そういえば、うちの首藤教授も患者さんにそうしてるなぁ。
患者さんのご自宅を回っていて、1番印象的だったのは、すべての患者さんが石賀先生のことを心から慕っている姿を見せていたことです。
もはやファンクラブかっ!と思うほど、石賀先生を信頼されており、患者さんが大満足している姿を見ることができました。まさに講演で聞いたことそのまんまを実践されており、自分まで幸せな気持ちになっていました。
自分も患者さんにこんな顔見せてもらえるかなぁと想像しながら、患者さんを診察したり、患者さんとお話させて頂いたりしていました。
6名の訪問診療が終わってから退院前カンファレンスにも参加させて頂いたこともとても良い経験でした。
石賀先生は移動中の車の中、昼食中など、とても気さくにお話してくださり、いつの間にか緊張も解け、こちらからも聞きたいことをたくさん聞かせていただくことができました。自分にとってかけがえのない素晴らしい経験でした。
クリニックに戻ってからは、石黒先生や中村事務長さんとゆっくりお話しさせていただいたり、クリニックの隅から隅まで見せて頂いたりと、とても有意義で楽しい時間でした。
この経験を、自分がこれからやっていく在宅医療にしっかり活かして、患者さんに還元していきたいですね。
石賀先生のように一人でも多くの患者さんから笑顔を引き出せたらと思います。
今回も本当に最高の見学でした。
石賀先生、看護師の岡田さん、中村事務長さん、そして「いしが在宅ケアクリニック」の皆様、この度は誠にありがとうございました。
また近い将来再訪させて頂きます!
みなさまへ
- By: 小笠原真雄 先生
- 7.Jun.2018
- Doctor 医療法人 聖徳会 小笠原内科
いしが在宅ケアクリニック
理事長・院長 石賀丈士様
事務部長 中村和親様
医師・看護師・事務・ケアマネジャー スタッフ一同様
平素より大変お世話になっています。
先日はレセプト期間中という非常にお忙しい中、笑顔で見学の受け入れをして頂き、誠にありがとうございました。
医療の面だけではなく、スタッフ間の雰囲気の良さも含めて大変勉強になりました。
小笠原内科において仕事の効率化、スタッフの働き方改革を重点的に進めていきたいと思っていた中で、いしが在宅ケアクリニックの理念あるいは院長自身の考え方に触れることができ、大変参考になりました。
皆様方の様な取り繕う必要 のないくらいの雰囲気のいいクリニックを目指して、頑張っていきたいと思っております。
今後も多大なるご迷惑をお掛けすることがあるかと思いますが、ご指導・ご鞭撻の程よろしくお願い致します。
医療法人 聖徳会 小笠原内科
小笠原真雄、巖后顯範、スタッフ一同
石賀先生、中村事務部長様へ
- By: 南大揮 先生
- 25.May.2018
- Doctor つばさクリニック
先日はお忙しい中、見学させて頂き、本当にありがとうございました。
石賀先生には移動中に、開業時やその後の運営において必要なことをいろいろと教えて頂きました。また、貴院の在宅看取りや緩和ケアへの取り組みは大変素晴らしいと思いました。
これから自分でクリニックを作っていくにあたって、地方で人を集めて行くには、どういった特色を出せるのかが
大変重要なことだと改めて感じました。
夕方に医局で先生方と情報交換の時間を頂けたのも大変良かったです。電子カルテのことを含め、とても参考になるお話が聞けました。
来年にはクリニックを新築予定とのことで、完成後にはぜひまた一度見学させて頂きたく存じます。
今後ともご指導のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
みなさまへ
- By: 若山哲平 様 / 足立 様、小寺 様
- 26.Feb.2018
- 事務長・看護師 医療法人 大垣在宅クリニック
石賀理事長、中村事務部長、そしてチームZAITAKUのみなさま、昨日はお忙しい中見学させていただきましてありがとうございました。
若山様
今回の見学で最も印象に残ったことは、組織マネジメントに関するお話しでした。
組織として目指す形があり、それを実現するためにはどうすれば良いのかを徹底的に考え、実践を積み上げて来られたことがよく分かりました。
「患者さんのため」、「地域のため」という大きな目標は共有し易いのですが、そこに至るまでの道のりをどう描き、どのように実行するのかというところまでしっかりと掘り下げて組織を作らなければ、持続性のあるクリニックにはならないということを実感しました。スタッフが疲弊しない仕組みを構築し、なおかつ診療の質を維持向上できる組織にしていきたい、していかなければならないと気持ちを新たにしました。
貴院で勉強させていただいたことを持ち帰り、より魅力的なクリニックにできるよう改善していきます。
足立様、小寺様
診療同行では、状態観察から医療処置、カルテ入力やコミュニケーションに至るまで、医師と看護師間でスムーズに業務分担されており、訪問時間がとても有効に活用されていると感じました。
貴院での終末期患者さんの8割は訪問看護ステーションを利用されており、ステーションとの密接な関りが必要であると伺う中で、連携の重要性を再認識しました。今後も地域で必要とされるクリニックとして存続できるよう、本日の学びを共有し改善出来ることから取り組んでいきたいと思います。
今村 好佑様
お忙しい中、石賀理事長、中村事務部長を始め、多くのスタッフの方々に当日はお世話になりました。とても親切かつ丁寧に教えて頂き本当にありがとうございました。
見学してまず感じたことは、とても明るい雰囲気であることに驚きました。終末期の医療と聞くともっと暗く、重いものを想像していましたが、いしが在宅ケアクリニックでは本当に温かく、穏やかでした。この点に関しては、石賀理事長より「暗く、重くなってしまったらこちらの負け」「医療機関を反面教師にしている」という言葉を聞いて、なるほど!と感心致しました。
今回の見学に臨むまで自分の浅い経験の中から"病気の療養は医師や設備の整っている大学病院が患者さんにとっても症状を緩和させ、療養のしやすい環境である"ということを信じて疑いませんでした。しかし、いしが在宅ケアクリニックの提供している医療と実際の患者さんとその家族を見て、それまでの自分の考えは非常に凝り固まったものであることに気が付いたのと同時に"在宅で死を迎えるということは、患者さん本人のQOLも高めることが出来、残される家族の死の受容にも繋がる"ということを再発見することが出来ました。
私たち保健師とは、対象の方へのアプローチの方法も果たす役割も異なりますが、本日見学させて頂いた中で見聞きし、学んだことは私にとって非常に有意義なものになりました。
本日は誠にありがとうございました。
新堂 愉香子様
私は、行政で、赤ちゃんからご高齢の方まで、町民の健康づくりを中心に仕事をしている保健師です。
今回の実習は、行政の保健師として、今後2025年問題に向け、地域包括ケアシステムを構築していく中で、現在、患者さんと直接の関わりは無いけど、今後どのような役割を担っていけばよいのか。在宅医療の現状をみせていただくことで、その一助にさせていただけたらという思いで実習させていただきました。
実際に、訪問診療に同行させていただき、まず感じたことは、先生と看護師さんの、患者さんやご家族とのコミュニケーションの良さでした。患者さんの話をしっかりと傾聴され、励まし、また、ご家族の不安や疑問にも丁寧に応え、患者さんやご家族が、先生方をとても頼りにしてみえるということを感じました。患者さんの病気だけ診るのではなく、患者さんを含めた家族全体を診て医療されていることを、とてもすばらしいと思いました。
そして、患者さん方が、とても自分らしく生活してみえる姿に触れることができました。
ペットを見て素敵な笑顔を見せてくださったり、バリアフリーになっていなくても、長年住み慣れた家でご夫婦仲良く生活している姿など、患者さんやご家族の笑顔に触れ、疾患を持ちながらも、在宅で生活できることの大切さを感じました。そのためには、信頼できる在宅医療があることが必要で、いしが在宅ケアクリニックの存在の必要性を再認識させていただきました。
地域包括ケアシステムにおいて、在宅での生活を勧めている背景には、医療費や介護給付費の抑制にありますが、今回の実習を通じ、本当に患者さんやご家族にとり、在宅で療養生活を送れることの幸せ、大切さを机上ではなく直に感じさせていただくことができ、今後、行政の保健師として、地域包括ケアシステムを考えていく上で、根幹とも言うべき貴重な実習をさせていただきました。
最後になりましたが、石賀理事長、中村事務部長をはじめ、先生方、スタッフの皆様には、とてもご親切にご指導いただき、感謝申し上げます。ありがとうございました。
見学の御礼と感想
- 29.Nov.2017
- 看護師、医療事務、広報 医療法人双樹会 よしき往診クリニック
看護師 田中 様
本日はありがとうございました。
また、門間先生、牛江さん、訪問同行させて頂きありがとうございました。
コピーやファックスが患者様宅で出来ることや、処置の物品をセット化されている事、
そして、先生と看護師さんの連携がスムーズで、患者さんやご家族に優しい言葉がけをされており、大変勉強になりました。本日学んだ事を、今後の業務にいかしていきます。
本日は本当にありがとうございました。
医療事務 山田様
昨日は、月末のお忙しい中、クリニック内見学や、事務作業について教えていただきありがとうございました。
4月に開院したばかりで、院内の事務作業についてまだまだ効率化を図るにはどうすればよいか、試行錯誤しているところでした。
早速取り入れることができる部分と、今後スタッフが増員していく上で考えていくべきことを想定するよいきっかけとなりました。
また、仕事をきちんとされる一方で、休暇も十分に取得されており、職員満足度も非常に高いように感じられました。こちらもすごく見習うべきところでした。
本当にありがとうございました。
今後とも学会等でお会いする機会等があるかと存じますが、よろしくお願いいたします。
広報 岩﨑様
昨日は見学の機会をいただき、ありがとうございました。
当院では患者数増加とともに組織の強化、業務効率の改善の必要性を感じておりましたので、とても勉強になりました。
また、中村さまとお話しさせていただき、新聞発行は病院の地域連携室や紹介元の先生との接点になるため、ぜひ取り入れたいと思います。
私自身も在宅医療に携わってみて、自宅で最後まで療養生活を送りたいという地域の需要は非常に高く感じております。
石賀先生が築かれた四日市モデルのように、当院だけではなく、行政や地域の多職種事業所と連携し、地域全体での見守り、看取り体制を創っていきたいと思います。
「まちづくり」にも関わりたいと考えておりましたので、非常に勉強になりました。
昨日は本当にありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします!
クリニックの皆様へ
- By: 二村 直行様
- 20.Jul.2017
- 薬剤師 マリーングループ
石賀理事長、中村事務部長を始め、スタッフの皆様にたくさんのことを教えていただきました。
今まで在宅医療に関わることはありましたが、医師の往診に同行するのは初めてで、とても貴重な経験となりました。薬剤師として訪問する際は、薬の説明や体調の確認など、患者様本人にスポットを当ててしまいがちでした。特に末期がんなど治療困難な疾患の場合、ご家族にどのような言葉をかけてよいものか迷うこともありました。しかし、いしが在宅ケアクリニックの医師・看護師の方々はご家族の方にも積極的に気を配り、一家全体をケアされていました。当たり前のことかもしれませんが、それこそが自宅での看取りを可能にしている秘訣なのではないかと感じました。
また、皆様がやりがいを持って働きながら、プライベートも充足させているのが印象的でした。在宅医療、特に個人在宅は忙しくて、スタッフに負担がかかるイメージが強くありましたが、仕組みをしっかり作ることで十分に改善できるということが分かりました。
これから在宅医療がもっと重要視されていく中で、自宅で最期を迎えたい患者様に対して、薬局薬剤師として何ができるかを考えながら業務に励みたいと思います。
本当にありがとうございました。
見学させていただいた感想
- By: 山科明彦 先生
- 16.May.2017
- Doctor ホームケアクリニックもみじ(副院長・訪問診療部長)
お忙しい中、石賀理事長、中村事務部長を始め、多くのスタッフの方々には、親切に教えていただき、本当にありがとうございました。
見学させていただいて、まず感じたことは、システムが非常にシンプルに構築されていることでした。在宅医療といえば、非常に難解な診療報酬制度に始まり、多くの職種との連携、スケジュールや物品の管理、スタッフのマネージメントなど、大変複雑なイメージがあると思います。しかし、いしが在宅ケアクリニックでは何事も分かりやすく、管理に多くの労力が要らないように考えておられると感じました。
また、スタッフのやりがいや働きやすさにも、非常に配慮されており、自分の生活を犠牲にするのではなく、プライベートも満喫できるよう考えられていました。それぞれのスタッフも、自分のするべき仕事がしっかり理解できており、能動的に働かれているのが印象的でした。
そのような診療が出来る一番の理由は、やはり石賀先生のリーダーシップだと感じました。石賀先生が明確な目標意識を持たれ、かつそれを共有(公言)することで、スタッフも同じ方向を向けるようにされていること、また、石賀先生の診療に同行したり、カンファレンスでフィードバックしたりすることで、石賀先生と同じレベルの診療を目指せるようトレーニングしておられたことが印象的でした。
在宅医療の道に踏み入れて、もう少しで3年になり、一医師として患者さん本位で、ご本人・ご家族を支える医療を担う自信はついてきましたが、24時間365日の安心を支えるには、多くのスタッフが必要となります。
広島市でも、やりがいがあり、働きやすい職場を作れるよう頑張りたいと思います。
クリニックの皆さんへ
- By: 姜琪鎬(かん きほ)理事長
- 18.Jan.2017
- Doctor 医療法人みどり訪問クリニック
本日はありがとうございました。
先生からはクリニックの組織マネジメントと、地域の支え方について、非常に実践的なお話を賜り感銘を受けました。すごいクリニックはレベルが違うと、ひしひしと伝わってきました。当院もやっと常勤医4名体制になりましたので、先生から教えていただいたことが、当院で役立つことを確信しました。
また、クリニックの皆さんも温かく出迎えていただきまして感激しております。
今回の学びを機に当院とも交流を深めていただければと思っておりますので、
今後も宜しくお願い致します。
スタッフの皆さん
- By: 波村美絵 様
- 18.Jan.2017
- 事務長 医療法人みどり訪問クリニック
石賀先生、中村事務部長さんを始め、スタッフの皆さんありがとうございました。
細かい質問にも笑顔で答えてくださり、居心地の良さを感じました。
いしが在宅ケアクリニックは、「医師がたくさん集まるクリニック」そして「看取り実績も西日本一のクリニック」ということで、大変興味がありました。
事務部長さんへお願いして、やっと見学ができてわかったことは、①貴院が、地域全体の中で在宅医療の役割を明確に理解され実践されていること、そして、②スタッフが支え合える環境が貴院の成長を支えていること、です。また、当院との業務フローとの違いから参考になる点も多く、業務を俯瞰するのに大いに役立ちました。貴院のスタンスの中で印象的だったのが、マインドを大切にされている点です。当院も同じスタンスなので、大変共感しました。定期的に情報交換していきたいです。ぜひ今後もどうぞ宜しくお願いします。
石賀 丈士 先生、中村 和親 様、スタッフの皆様
- By: 池田和也 先生
- 22.Dec.2016
- Doctor 医療法人社団 いいざか 池田医院
お忙しい中、私達の研修の受け入れをして頂き、ありがとうございました。クリニックさんは、想像以上にシステムが合理的で、医療は丁寧で、感動しました。石賀先生は、とても情熱的で人格者で、カリスマ性を感じました。また、短い時間でしたが看護師の牛江さんや、スタッフドクターのみなさんといいお話ができて嬉しかったです。
現在、今後の自分達の在宅医療の方向性に行き詰まりを感じ、迷っていたところでしたので、たった1日の研修でしたが、今すぐに改善しなければならない課題や将来的な計画の選択肢が明確になり、非常に有意義でした。
また機会がありましたら、皆様にお会いしたいし、その後のご報告をさせて頂きたいと思います。本当にありがとうございました!
いしが在宅ケアクリニック様
- By: 大塚賢司 先生
- 22.Dec.2016
- 薬剤師 ファーマライズ薬局泉店
先日は大変お世話になりました。
1日往診に同行させていただき、新たな発見、驚きがたくさんありました。
以前から薬剤師は在宅業務において何が出来るか、何を求められているのか、を常日頃自問自答していましたが、石賀先生やスタッフを見て、患者と患者家族が最後まで満足のいく生活のお手伝いをしたいと思いました。
病院に入院している時にも、もちろん家族との関係性は大切ですが、在宅医療においては、家族との関係性がさらに重要になり、どこまでフォローできるか、支えることが出来るかも私の課題になりました。
高齢者が増加傾向にあるので今後病院や診療所に行けない高齢者は増えてくると考えられ、今よりも在宅医療が重要な診療形態になってくると思うので、その診療形態の中に薬局、薬剤師が関われるように今後も地域医療の輪に入れるよう努めていきたいと思います。
薬剤師が在宅医療に携わった歴史はとても浅く、今後も悩むことは多々あると思いますが、今回の見学で見て、感じたことを忘れず、患者や患者家族へ後悔のない生活を提供できるようこれからも在宅医療に貢献していきたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
いしが在宅ケアクリニック御中
皆様へ
- By: S.H様
- 28~30.Sep.2016
- 医療事務 京都市内科医院
温かく優しい雰囲気の中、相談外来では患者様のお話を丁寧に傾聴され、患者様のお身体の常態はミーティングで共有し、事務的な作業は書類管理で徹底されているのを拝見し、チームワーク医療の心髄、業務の基盤を学ぶことができました。
訪問先では患者様が笑顔や安堵感で包まれるご様子を拝見し、在宅医療は医療行為だけでなく、寄り添う大切さがある事を痛感しました。
また、医師が「患者様にとっての幸せは何か、“いのち”のサポートをどうすれば良いか」を語られ、スタッフの方が「医師を支えるのが私の仕事」と話される熱い想いにも心打たれました。
在宅医療の奥深さを学ばせて頂けたことは、私の財産となりました。
ありがとうございました。
先日、2日間の見学をさせていただき、ありがとうございました。
私はこの夏、教職経験研修でマネジメント力・コミュニケーション力・コーディネート力を活かす方法を学びましたが、クリニックのスタッフの皆様はすでにその力を現場で活かされ、不安や悩みを抱えていのちと向き合っている患者様やご家族の方の思いを、丁寧に受け止めて治療をし、心身ともに支えてみえる姿も拝見いたしました。
患者様のみでなくそのご家族の方の体調を必ずうかがいながら訪問診療されている様子に、求める医療のかたちがここにはあるように感じました。
訪問先では、すべての方が先生や看護師さんに感謝の気持ちを伝えてみえました。丁寧に寄り添うことで信頼関係を築けていることや、職場の雰囲気もとてもよくスタッフの皆さんがチーム医療として繋がっていることが反映されていて、学校現場にも必要なチーム力であると考えさせられました。
医療現場で向き合ういのちと教育現場で向き合ういのち、私達が「いのちを守りたい」という思いでいるのは同じです。そして、「寄り添う」「心身ともに支える」姿勢は養護教諭も同じです。
こちらでの経験は「いのち」をみつめる時間となりました。
この体験を通して、今後すすめる「いのちの教育」につないでいきたいと思っております。
クリニックの先生方、看護師の皆様、スタッフの皆様、訪問させていただきました患者様やそのご家族の皆様、本当にありがとうございました。
全国自治体における歳出(年間支出)のうち医療・各種福祉関連予算の割合が増加しているにも関わらず少子高齢化の影響で税収の伸びが期待出来ないことから、従来実施してきた各種行政サービスを見直さざるを得ない所が急増しています。しかし「いしが在宅ケアクリニック」の革新的な手法が普及すれば医療の質を落とすことなく、国全体の医療費の削減と質の高い在宅医療の提供が可能になる点に厚生労働大臣も注目しています。
石賀院長は長時間勤務が常態化した過酷な医療現場での勤務経験を基に、先進情報機器の積極活用や様々な工夫を重ね医師の負担軽減と事務手続きの簡素化を実現。さらに患者本人だけでなく、介護にあたるご家族からも寄せられる様々な悩みやご相談にスピーディーに対応する
ことで三者(患者・ご家族・医療チーム)が常に笑顔で質の高い生活(QOL)を送る事を可能にしました。
併せて注目すべき点として「医療は命に関わるサービス業」を基本理念に、石賀院長は各分野でトップクラスの才能を発揮してきたドクターを結集し、「若き改革派市長」として全国に行政手腕が知れ渡った「前松阪市長、山中光茂先生」もチームに加わりました。
視察で訪問診療に同行させていただいた際、患者さんそしてご家族からの「いしが在宅ケアクリニックと出会っていなければ私たちはどうなっていたでしょうか、本当に助かってますありがとうございます!」と笑顔でドクターや看護師さんの手を何度も何度も握り締めるお姿を拝見し、胸の奥底から熱いものが湧き上がってきました。 日本の在宅医療充実のために、今後ますますのご活躍をご祈念申し上げます。
見学を終えて
- By: 永井 康徳 理事長
- 30.JUN.2014
- doctor 医療法人ゆうの森たんぽぽクリニック
石賀先生には、ゆうの森の見学にもお越しいただき、随分お若いのにビジョンがしっかりされており、在宅医療を行う次世代の有望な方だと思いました。
四日市市では、医師会や行政ともコラボレーションをされて、在宅での緩和ケア、終末期医療に特化されて、圧倒的な看取り実績をあげて、四日市の医療を変えたといわれている先生です。
在宅での看取り数は全国でもトップクラスを誇っており、多くの医師や看護師が集まってくるクリニックとなりました。多死社会に向けて在宅医療は鍵となる存在です。いしが在宅ケアクリニックはこれから全国の在宅医療を担う存在となること間違いなしです。さらなる発展を願っております。
見学研修を終えて
- By: 吉川先生
- 14.JUL.2015
- doctor 愛北ハートクリニック
約1カ月間、訪問診療に帯同し研修させて頂きました医師の吉川です。これまで急性期総合病院に勤務してきました。訪問診療では医療者と患者さんの距離の近さに大変驚きました。物理的な距離では入院設備のある病院の方が当然近いわけですが、ご自宅にて診療させて頂き24時間体制を敷くことが患者さんとの心の距離を大変に近しくしている事を実感致しました。
私も愛知県一宮市に訪問診療のクリニックを開業致します。患者さんとの心の距離が近い診療を心掛けていきたいと思っております。初めての事だらけでしたが、患者さん方やクリニックスタッフの方々に支えて頂き研修を終えることが出来ました。ありがとうございました。